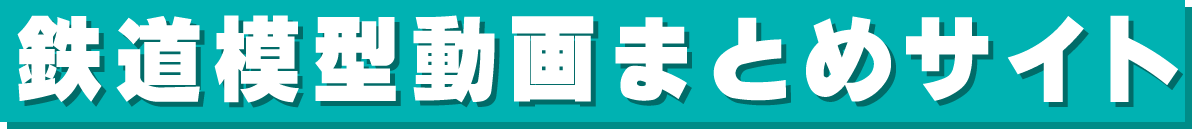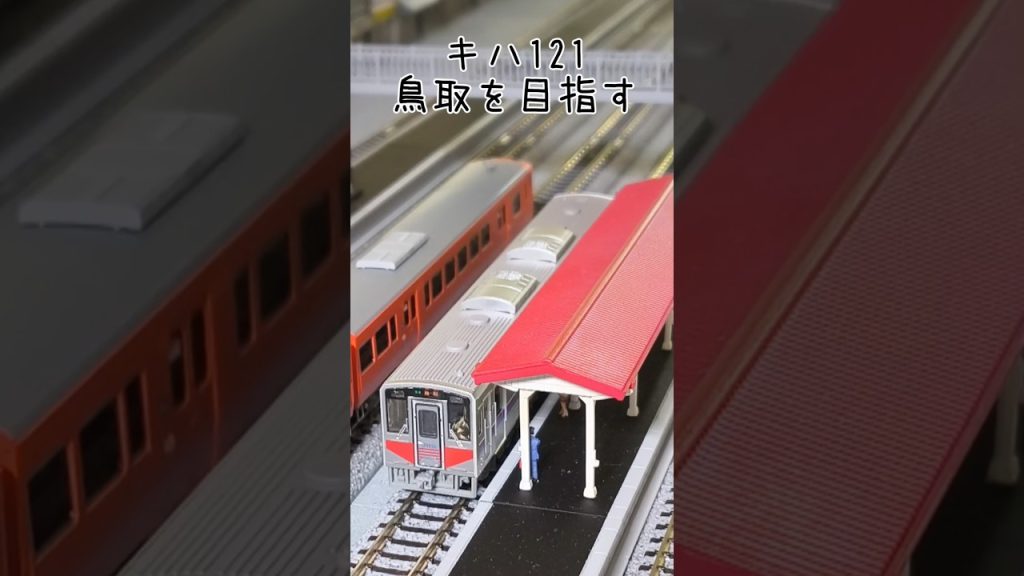鉄道模型の最安値を探す!

おすすめの鉄道模型動画
北陸新幹線は、東京都から上信越・北陸地方を経由して大阪市までを結ぶ計画の高速鉄道路線(新幹線)であり、整備新幹線5路線の一つです。2024年(令和6年)3月16日時点で、群馬県高崎市の高崎駅から福井県敦賀市の敦賀駅までの間が開業しています。運営主体は高崎~上越妙高間がJR東日本、上越妙高~敦賀間がJR西日本です。
『鉄道要覧』では高崎駅を起点としていますが、整備新幹線としては東京都が起点で、高崎以東については、東京(東京都千代田区)~大宮(埼玉県さいたま市大宮区)間は東北新幹線、大宮~高崎間は上越新幹線と共用しており、列車は上越新幹線および東北新幹線を経由して東京駅まで乗り入れている。旅客案内上は東北・上越新幹線の東京~高崎間を含む東京~敦賀間が「北陸新幹線」と案内されています。2015年(平成27年)3月13日までは長野駅が終点であり、1997年(平成9年)の開業当時は「長野行新幹線」、後に「長野新幹線」と呼ばれていました。
北陸新幹線は1972年(昭和47年)に、全国新幹線鉄道整備法第4条第1項の規定による『建設を開始すべき新幹線鉄道の路線を定める基本計画』により公示され、1973年(昭和48年)11月13日に整備計画が決定された5路線(いわゆる整備新幹線)の路線の一つです。国鉄の財政悪化により建設が一時凍結されましたが、1989年(平成元年)に高崎~軽井沢間で着工され、1998年(平成10年)に開催される長野オリンピックに合わせて1997年(平成9年)10月に高崎~長野間が整備新幹線としては初めて開業しました。長野~金沢間は一部区間がスーパー特急方式で着工された後、全区間がフル規格化され、2015年(平成27年)3月に長野~金沢間が開業しました。金沢~敦賀間は2012年(平成24年)に着工され、2024年(令和6年)3月16日に開業しました。
1997年(平成9年)の開業時点では長野駅が終点であり、2015年(平成27年)の延伸まで北陸新幹線は北陸地方に達していなかったことから旅客向けには当初「長野行新幹線」、後に「長野新幹線」と呼称していました。JR東日本管内の駅の北陸新幹線の乗り換え案内では「北陸(長野経由)新幹線」、「北陸新幹線(長野経由)」など「長野経由」まで表示されています。
鉄道建設・運輸施設整備支援機構が鉄道施設を建設・保有し、高崎~上越妙高間はJR東日本、上越妙高~敦賀間はJR西日本により運営されています。JR東日本・JR西日本の施設管理境界は上越妙高駅の金沢方・高崎起点177 km950 m地点です。同一名称の新幹線の路線が複数の鉄道会社によって運営されるのは、北陸新幹線が初めてであり、現在でも唯一です。なお、JR西日本は北陸新幹線とは別に山陽新幹線(新大阪駅 – 博多駅)も運営しており、JR東日本に続いて複数の新幹線路線を運営する鉄道会社となり、1つの鉄道会社が運営する新幹線の路線が直接つながっていない初の事例ともなりました。
東日本と西日本に跨って電源周波数が異なる地域を直通しており、50Hzと60Hzの交流電化区間が混在する唯一の新幹線でもあります。北陸新幹線は整備新幹線として初めて着工され、電源周波数が異なる地域や山岳地帯、豪雪地域を経由する路線でありながら工事費を抑えるために様々な新技術が用いられています。
高崎~上越妙高間(JR東日本区間)が旧信越本線、上越妙高~敦賀間(JR西日本区間)が旧北陸本線と概ね並行するルートを通っています。これら並行在来線は新幹線区間開業後は一部を除いて第三セクターやバスに転換されました。
未着工区間である敦賀~新大阪間については、2019年(平成31年)5月に環境アセスメントのために福井県小浜市と京都駅(京都府京都市)を経由する概略ルート(通称:小浜・京都ルート)が公表されています。一方で敦賀駅延伸開業の2024年現在でも着工しておらず、新大阪駅延伸開業は2046年を予定しています。京都府の一部地域などの反対や滋賀県を通る湖西線の並行在来線問題などを抱えており、京都駅付近は詳細なルートも決定していない状態にあります。この間、京阪神と北陸地方との移動は敦賀駅での乗り換えを強いられることになるなど、もともと京阪神との関係性が深かった北陸における関西の影響力低下が不安視されているようです。
新幹線E7系・W7系電車は、JR東日本・JR西日本の新幹線車両(新幹線電車)です。JR東日本所有車がE7系、JR西日本所有車がW7系となっていますが、呼称及び車内チャイム以外において仕様に差異はないことになっています。
北陸新幹線長野~金沢間延伸開業に際し、JR東日本・JR西日本が共同開発・導入した車両で、新規に設定された「かがやき」「はくたか」「つるぎ」のほか、東京~長野間で1997年から運転されている「あさま」で運用されています。また、2018年度より上越新幹線東京~高崎 – 越後湯沢 – 新潟・ガーラ湯沢で運用されています。
工業デザイナーの奥山清行がデザインを手掛けました。
系列名は、JR東日本所有車はE1系以降に制定された同社の新幹線車両系列名付与方法に準じE7系、JR西日本所有車もこれに準じる形でW7系が付与されました。また、JR西日本の車両の系列名にWが付与されるのはこれが初めてです。
基本仕様は、最高速度がE2系と同じ260 km/h、編成はMT比10M2Tの12両とした上でE5系に引き続きグリーン車より上級クラスのグランクラスを導入。定員はグランクラス18名・グリーン車63名・普通車853名の計934名でしたが、荷物置き場設置により普通車10名減の843名、計924名に変更となりました。
製造はE5系・H5系を製造した川崎重工業車両カンパニー(2021年〔令和3年〕10月1日以降落成分は分社独立により川崎車両名義)・日立製作所笠戸事業所のほか、総合車両製作所横浜事業所がE7系のみ、近畿車輛がW7系のみを担当しました。北陸新幹線金沢開業時点での投入予定編成数はE7系が17編成、W7系が10編成の27編成計324両でした。
2011年12月13日に毎日新聞が「北陸新幹線延伸開業時の車両はE2系をベースにした新型車両をJR東日本が導入する方針」と報じ、翌14日には北陸地方を基幹とするメディアも一斉に報道しました。2012年1月にJR西日本区間を所管する同社金沢支社長が定例会見でJR東日本との共同開発方針にを言及、雪害対策の必要性から開業1年前となる2013年冬シーズンに実車試験を予定しているとの趣旨を発表しました。同年9月4日にJR東日本・JR西日本両社で共同開発の公式発表を行いました。